海兵隊の創設と任務
1775年4月、イギリス軍とアメリカ大陸植民地の民兵が衝突して、アメリカ独立戦争が勃発しました。そして、同年5月から1781年まで続くことになる第2回大陸会議が、アメリカ大陸のフィラデルフィアで開催されました。そこには、13植民地(アメリカ大陸に移民してきたイギリス人によって建設された東海岸沿いの植民地)の代表が集まりました。会議では、植民地軍が創設され、ジョージ・ワシントンが植民地軍の総司令官に任命されました。
1775年10月と11月には、イギリス本国からアメリカ大陸への海上輸送を妨害するため、海軍と海兵隊が創設されました。当初、海兵隊は海上での武力衝突を支援する任務に就いていました。そして、海兵隊はアメリカ独立戦争の勝利に貢献しました。その後、海兵隊は、一時解散しましたが、再び設立されました。現在まで上陸作戦など数々の任務を果たしてきました。

しかし、その任務は拡大・進化していきました。すなわち、海兵隊は、海上から敵地に真っ先に上陸する軍事作戦を遂行するとともに、時には、内陸深くまで進攻して敵を制圧する軍事作戦なども遂行してきました。さらに、海兵隊は、紛争地域において自国民の保護や退避を行ったり、災害において自国民の捜索や救助を実施したり、人道支援や災害復旧の活動に従事したりするなどの様々な任務を果たしてきています。
海兵隊は、後続する陸軍の進攻路を切り開くため、先頭に立って海上から敵前上陸を行う水陸両用作戦を本務とする部隊です。そのため、海兵隊は、先陣を切って敵軍を切り崩す「殴り込み部隊」とも呼ばれています。また、海兵隊は海外での戦闘を前提としている即応部隊です。そのため、本国の防衛は本来の任務には含まれていません。

すなわち、海兵隊は即応部隊として戦闘地域に真っ先に駆けつける機動力を優先しています。そして、海兵隊は、大砲、戦車、艦船、戦闘機などの陸軍・海軍・空軍が有する兵器や能力も備えています。それによって、海兵隊は、自前の装備で様々な作戦を独自に遂行することができます。これが海兵隊の最大の特徴でもあります。
海兵隊の組織
海兵隊は、海軍省に属していますが、陸軍、海軍、空軍に次ぐ第4軍として独立した軍事組織です。ちなみに、アメリカ軍には、この4軍に沿岸警備隊と宇宙軍を加えて6つの軍事組織があります。そして、海兵隊は海外に緊急展開する即応部隊として約18万人の兵員で構成されています。
海兵隊総司令官は、海兵隊の最高司令官として国防総省に属する統合参謀本部に配置されていますが、軍事作戦を指揮するのではなく、海兵隊を維持管理するための行政を指揮・監督します。すなわち、地域別の統合軍司令官が実際の軍事作戦を指揮することになっています。そして、海兵隊の部隊は配置された統合軍の下で行動することになります。
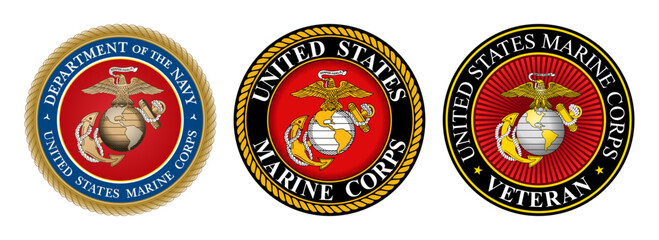
海兵隊は、軍事作戦などを遂行するうえで独特な組織編制を行っています。すなわち、海兵隊は、海兵空陸機動部隊(MAGTF(マグタフ): Marine Air-Ground Task Force)と呼ばれる部隊編制を基本としています。MAGTFは、司令部、陸上部隊、航空部隊、兵站(補給)部隊の4つの組織によって構成されています。司令部は、情報、通信、管理などの部署で構成され、各部隊を指揮統制します。

陸上部隊は、歩兵、砲兵、偵察、装甲、水陸両用車両、工兵などの部隊で構成され、陸上作戦を実施します。航空部隊は、飛行隊などで構成され、航空機による偵察、戦闘、輸送などの航空作戦を実施します。兵站部隊は、糧食、燃料、弾薬、装備などの補給や装備品などの修理を担当します。この部隊編制によって、海兵隊は、海又は空から、時には両方から必要な場所に上陸して進攻することができます。
そして、海兵隊は、紛争などに迅速に対応するため、作戦の規模や目的などに応じて組織の規模を柔軟に変えることができます。すなわち、海兵隊は組織の規模によって次の3段階に変化します。それは、海兵遠征軍(MEF(メフ): Marine Expeditionary Force)、海兵遠征旅団(MEB(メブ): Marine Expeditionary Brigade)、

海兵遠征部隊(MEU(メウ): Marine Expeditionary Unit)という3つの戦闘組織です。その中で、MEFが最大の編成軍です。MEFは、大規模な有事や危機に対応する主要な戦闘組織で、20,000~90,000人の兵員によって構成されています。そして、60日分の物資を保有して、いかなる条件下でも、上陸と陸上での軍事作戦を実施することができます。
MEBは、海兵遠征軍の次の段階の規模を持つ戦闘組織で、最大15,000人の兵員によって構成されています。そして、30日分の物資を保有して、MEFと同様に軍事作戦を実施することができます。MEUは、前方展開する機動部隊で、最大2,200人の兵員で構成されています。そして、15日分の物資を保有して、MEFやMEBと同様に軍事作戦を実施することができます。

前方展開とは、同盟国などを守るため、敵対国の脅威に対処する目的で、戦略的に重要な海外の拠点に部隊を配置することです。そして、MEFには、Ⅰ~ⅢMEF(第1~第3海兵遠征軍)という3つの常設軍があります。ⅠMEFの司令部は米国本土カリフォルニア州の海兵隊基地にあります。ⅡMEFの司令部は米国本土ノースカロライナ州の海兵隊基地にあります。
ⅢMEFは沖縄県の海兵隊基地に司令部を置いています。そして、ⅢMEFの多くの部隊は日本にある海兵隊基地に駐留しています。ちなみに、ⅢMEFは、第3海兵師団、第1海兵航空団、第3海兵兵站群、第3海兵情報群、第31海兵遠征部隊によって編成されています。そのほか、必要に応じで、予備役などによって編成される海兵遠征軍があります。
海兵隊の変革(新戦略)
海兵隊は、戦闘地域に緊急展開して、海や空又は両方から敵地に上陸して進攻したり、内陸での戦闘を実施したり、航空機による攻撃を行ったりする即応部隊としての任務を果たしてきました。一方、アメリカは、現在、中国の存在を経済や軍事の観点から最大の脅威と位置付けています。軍事面では、西太平洋地域における中国の海洋進出に対して強い警戒心を抱いています。
特に、アメリカは、中国が台湾有事の際に設定する第1列島線を安全保障上の強い懸念事項と考えています。そして、それに対抗する手段を計画しています。第1列島線とは中国が一方的に設定した軍事上の防衛線のことです。すなわち、中国は、九州沖から沖縄、台湾、フィリピンを経て、南シナ海を囲む線の内側の海を自らの勢力圏としています。

中国は、アメリカ軍がこの勢力圏に接近しないようにするため、「接近拒否戦略」を実行すると考えられています。そのため、中国は、空母などの海軍力や中国本土から発射されるミサイルの攻撃力を増強しています。このような中国の動向を踏まえ、アメリカの国防戦略は、これまでの内陸におけるテロとの戦いから、大国による勢力拡大を阻止するため、海上や沿岸などでの戦いに重点を置く戦略にシフトしてきています。
これによって、海兵隊の軍事作戦は内陸での戦闘から沿岸での戦闘に変わることになるため、海兵隊は、大砲や戦車などを使った野戦よりも、本来任務としての水陸両用作戦に比重を置くことになります。そのため、海兵隊は、海軍との強い連携に基づいた部隊の編制や装備を整えることが必要になりました。すなわち、陸上の戦闘で活躍した戦車大隊は廃止されて、海兵沿岸連隊が創設されました。

海兵沿岸連隊は、敵に発見されないように小規模の部隊に分かれて隠密かつ迅速に行動することになります。そして、海上から戦略的な拠点となる島の沿岸に上陸して陣地を確保することを目的とします。そこから、敵の艦艇や航空機を偵察したり攻撃したりします。このような任務を果たすため、海兵隊は、高い機動力を有する水陸両用車両や兵員輸送用航空機、敵の艦艇や航空機などを攻撃するための対艦・対空ミサイルやドローン兵器などの装備を十分に整える必要があります。
そして、海兵隊はこれまで以上に海軍との連携が重要になります。このような変化に対応した海兵隊(海兵沿岸連隊)は、中国の接近拒否戦略に基づく防衛網をくぐり抜けて、第1列島線の内側で任務を実行することが期待されています。つまり、海兵隊は、第1列島線の内側で、中国軍の情報を収集するとともに、中国軍に対して効果的な攻撃を加えることが期待されています。

アメリカ海兵隊に所属している最新鋭の航空機を紹介するね!

戦闘機ライトニングⅡ(F-35B)は、最高速度がマッハ1.6で、ステルス性(レーダーに感知されにくい特性のこと)が優れ、短距離離陸と垂直着陸が可能だよ!

輸送機オスプレイ(MV-22)は、ヘリコプターのように垂直離着陸やホバリングが可能だけど、以前使用していたヘリコプター(CH-46)と比較すると、最高速度は約2倍(時速約520km)、航続距離は約5倍(約3,900km)、輸送人員は約2倍(24名)の能力があるよ!













コメント